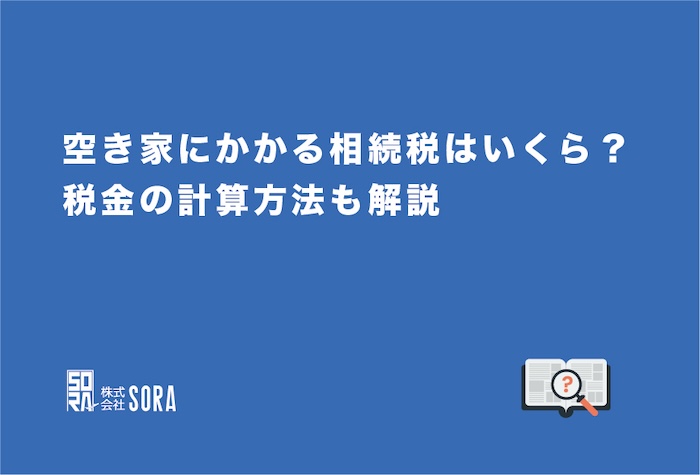親から空き家を相続した際、「使っていない家に税金がかかるのか」「誰も住まない空き家をどうすべきか」と悩む方は少なくありません。
空き家であっても土地や建物には資産価値があるため、原則として相続税の対象となります。
この記事では、空き家を相続した場合の税金の扱いや、賢く節税するための具体的な対策方法をわかりやすく解説します。
空き家の相続税はどうなる?

空き家であっても、被相続人(亡くなった方)が所有していた時点の土地・建物の評価額に応じて相続税が課されます。
誰も住んでいない状態でも、課税の「対象外」にはなるわけではありません。
ただし、住居として利用されていた空き家の場合は土地・建物の評価額が減額される特例があります。
誰も住んでいない空き家
相続した空き家に誰も住まず、居住用として利用していない場合、その不動産は「非居住用」として扱われます。
この「非居住用」の土地には、評価額を減少させる「小規模宅地等の特例」のような特例は適用されません。
この特例が使えないため、空き家の土地は課税評価額がそのまま計算され、結果として相続税の評価額が高くなります。
誰も住んでいない場合は、この節税効果の高い特例の恩恵を受けられない点に注意が必要です。
自宅として利用していた空き家
被相続人(亡くなった方)が生前に自宅として住んでいた空き家であれば、一定の条件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適用されます。
この特例を利用すると、土地の評価額が最大80%減額され、相続税の負担を大幅に軽減できます。
たとえば、故人と同居していた親族がそのまま住み続ける場合や、別居していた相続人が相続後に居住を開始した場合などが対象です。
または賃貸で貸し出していた場合(賃貸事業の場合は50%減額)もこの特例が適用されます。
ただし、相続開始後にすぐ売却してしまうと特例が使えないこともあるため、適用条件を事前に確認しておくことが重要です。
空き家の相続税の計算方法
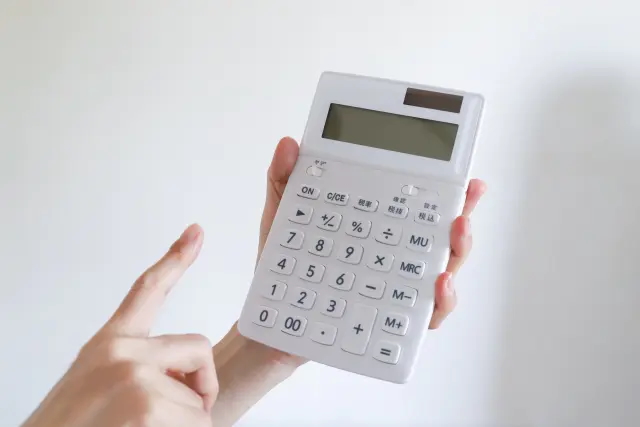
空き家の相続税は、原則として「土地」と「建物」の評価額をもとに算出されます。
土地と建物の評価額は実際の取引金額(時価)ではなく、建物部分は「固定資産税評価額」が基準となり、土地部分は「路線価方式」または「倍率方式」を基準に評価されます。
相続税の評価額は実際の取引金額(時価)よりも低くなるケースが多いですが、都市部など地価の高いエリアでは路線価が高く、評価額が高くなる傾向があります。
計算の基本式は以下の通りです。
相続税評価額 = 土地の評価額 + 建物の評価額
この合計額をもとに、他の財産(預金・有価証券など)と合わせて課税価格を算出し、基礎控除額を差し引いたうえで相続税率をかけて計算します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、相続人が2人なら4,200万円までは非課税です。
したがって、空き家の評価額が高い場合は、基礎控除を超える分に相続税が課される可能性があります。
そのため、空き家の相続税を安くするためには、相続税の特例を利用するなどして評価額を下げるのがポイントになります。
空き家の相続税対策でできることは?

空き家を相続すると相続税が発生しますが、生前贈与や様々な特例を利用することで、税負担を軽減できます。
ここでは、空き家を相続する際の相続税対策として効果的な方法を4つ紹介します。
生前贈与で相続財産を減らす
相続税を軽減する有効な方法の一つが、生前贈与によって相続財産をあらかじめ減らすことです。
毎年110万円までの贈与は「基礎控除」で非課税となるため、時間をかけて財産を移すことで相続税の負担を抑えられます。
また、住宅取得資金や教育資金の一括贈与特例を活用すれば、非課税枠を拡大できます。
贈与税は相続税よりも高い税率なのが一般的ですが、相続財産の内容によっては贈与税の方が安くなる場合もあるため、生前のうちに税理士などの専門家へ相談し、計画的に進めることが大切です。
誰も住んでいなければ賃貸に出す
空き家を放置せず、賃貸物件として活用することも効果的な相続税対策です。
家賃収入を得られるだけでなく、「貸家」として評価額が大きく下がり、相続税の課税対象額が減る場合があります。
特に土地部分は「貸家建付地」として評価され、評価減が適用される可能性があり、高い節税効果が期待できます。
多くの地主が相続税対策としてアパート経営を行うのは、この「貸家建付地」による評価減が受けられるためです。
また、第三者が住むことで、建物の劣化防止や防犯面でもメリットがあります。
ただし、リフォーム費用や管理の手間もかかるため、賃貸経営として成り立つかを慎重に判断しましょう。
生前に売却して現金化する
生前に空き家を売却して現金化しておくことも、相続税対策として有効です。
不動産の評価額が高いと相続税が増えるケースがありますが、現金化すれば相続財産の把握と納税準備がしやすくなり、相続人間での分割もしやすいためトラブルを防げます。
また、空き家を放置すると老朽化や固定資産税の負担が続くため、市場価格が高い時期に売却することは資産の有効活用につながります。
ただし、売却益に対して譲渡所得税が発生する場合があるため、事前に税額を試算しておくことが重要です。
相続後に売却して所得税の特例を使う
相続後に空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。
これは、一定の条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例で、所得税・住民税の負担を大幅に軽減できます。
対象となるのは、被相続人が一人暮らしで亡くなった後、一定期間内に売却した場合などです。
この特例を活用すれば税負担を抑えつつ資産整理が可能ですが、期限や適用条件が細かいため、早めに税理士や不動産会社へ相談することが大切です。
まとめ
空き家を相続すると、誰も住んでいなくても相続税が発生する可能性があります。
非居住用のまま放置すると税負担が大きくなりますが、居住、売却、賃貸活用などの対策で節税が可能です。
ただし、空き家の相続税対策は生前に行うのが基本であり、相続後にできることは限られます。
空き家を「負担」ではなく「資産」として有効に活かすために、専門家への相談も含めて早めの対応を検討しましょう。